もうすぐ新米の季節!なぜおいしいの?そのヒミツとは

9月から10月にかけて、ようやく朝晩の暑さから解放される時期、店頭には待ちに待った秋の味覚、「新米」が並びはじめます。
収穫したばかりの田んぼの恵みは、やわらかくツヤがあり、口に含むとほんのりとした甘みや旨みが広がるのが魅力です。
「新米」=おいしい! というのは、多くの人が持つ共通の意識だと思います。その一方で「なぜおいしいのか?」について詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、新米のおいしさについて、新潟薬科大学応用生命科学部の特任教授・大坪研一先生にお話を伺いました。
お話を聞かせてくれた人
大坪研一(おおつぼけんいち)先生
新潟薬科大学・応用生命科学部・応用生命科学科特任教授。農学博士。
農水省に入省後、1981年に農業・食品産業技術総合研究機構・食品総合研究所に配属し「お米の品質利用」をテーマにおいしさの評価、DNA品質判別、加工利用について研究を重ねる。その後、食品総合研究所・食品素材科学研究領域長を経たのち、現在は新潟薬科大学で、お米の機能性成分を病気の予防や健康寿命の延伸にも役立てようとさらに研究の幅を広げる。
著書に「日本一おいしい米の秘密」(講談社+α新書)、監修本に「再発見!コメの魅力 お米の未来」(日本食糧新聞社)など。メディアへの出演も多数。
聞き手: ソラミドごはんくん
ごはんが大好き!
ちょっぴりヒツジに似たごはんの妖精。好奇心旺盛で、ごはんのことなら何でも知りたい!聞きたい!見てみたい!と思っている。

「新米」と「古米」、それぞれの定義とは?


実はそれらの定義には2つの方法があるんです。
ひとつは、国が定める「米穀年度」を基準とする方法です。この方法によると、11月1日から翌年の10月31日までに収穫されたお米が「新米」、それ以前に収穫されたものが「古米」とされます。
もうひとつは、「JAS法(日本農林規格等に関する法律)」を基準とする方法。店頭で販売されているお米の食品表示はこのJAS法に基づいており、一般的にはこちらの基準で認識されています。JAS法および食品表示法に基づく食品表示基準では、収穫された年の12月31日までに包装または精米されたお米が「新米」とされ、それ以降のものは「新米」とは表示できません。翌年の11月1日以降は「古米」として扱われます。
なるほど〜。収穫されてからの期間が「新米」と「古米」を分ける基準となっているようですが、それらには味の違いもあるんですか?

お米のおいしさを表すときに用いられる「食味」についても大きな違いがあります。
これは、炊飯したお米について、外観、味、香り、粘り、硬さ、総合評価の6項目で判定する官能評価に基づいているのですが、次のようにいずれの項目においても、新米は古米よりも優れていると評価されています。
外観:白くてツヤがある
味:甘みと旨みが強い
香り:嫌なにおいがしない
粘り:粘りが強い
硬さ:やわらかい
総合評価:古米よりも総合的においしい
収穫後、時間が経つにつれ「食味」が落ちていくのですね。では、その原因となるものは何なのでしょうか?

1つ目の原因は、お米の「生命力」が衰えるということです。そもそも稲の種子であるお米は、生物として発芽する力、つまり生命力を持っています。ですが、時間が経つにつれ発芽が困難になり、同時に、甘みや旨みを生成する分解酵素の働きも弱まるのです。
さらに、「化学的変化」も原因となります。お米の甘みや旨みの基となるデンプン、タンパク質、脂質が時間とともに少しずつ自然分解されるために、食味が落ちていくのです。
加えて「物理的変化」で米粒が硬くなって炊飯のときに水を吸いにくくなるため、炊飯したときに新米と比べて硬めのご飯になります。
ですが、そもそもお米は、人の健康に大きな影響を与える機能性成分が少ないため、新米も古米も栄養価に関しての差はほとんどないんですよ。
ということは、おいしいお米の評価となる「食味」によって、ぼくたちは新米に魅力を感じているのですね。

その通りです!
「新米」がおいしいそのワケとは?

では、新米のおいしさである「食味」を生み出す根拠となっているものは、一体何なのでしょうか?

もっとも大きな根拠となっているのは、吸水力です。新米は細胞の壁がやわらかく、お米の中まで素早く水が浸透します。そのため、炊飯の際にデンプンが糊状になる糊化(アルファ化)が進みやすく、日本人好みのやわらかく粘りのあるご飯が炊けるのです。
次に、お米の主成分であるデンプン、タンパク質が豊富だということも理由です。加熱することにより、デンプンは甘みのもととなるグルコースに、またタンパク質は甘みや旨みのもととなるアミノ酸に分解され、それらがおいしさに直結します。さらに、新米ならではの香りの良さも、おいしさを感じる理由の一つです。
お話の中で、新米は吸水力が高いと言われましたが、そうなると、炊飯に欠かせない「水」にもこだわった方が良さそうですね。どのような水が適しているのかも教えてください。

お米の水分量は13〜15%ですが、ご飯の水分量は約60%と半分以上を占めます。つまり、水はご飯のおいしさに大きく影響するのです。
日本には、一般的に炊飯に適していると言われている軟水が多く、おいしいご飯が炊けると言えるでしょう。
ただ、近年の地球温暖化によって高温障害を受けたお米の場合、硬水で炊いたほうが水分をしっかりと含んだ崩れないご飯に炊き上がるという報告もあります。しかもこの場合、硬水に含まれるカルシウムも摂取できるという利点も。どのようなお米を炊くのかによって水を使い分ける、ことが大切だと言えますね。
「新米」の魅力とは?

「新米」のおいしさのヒミツがよくわかりました!次に、長年お米の研究を続けている大坪先生に、「新米」の魅力についてもお聞きしたいです。

なんと言っても、炊飯したときのご飯のツヤですね。
「銀シャリ」と呼ばれるように、白くピカピカと輝くご飯は新米ならではの魅力です。香りや甘み、旨みといった味わいも、古米に比べ格別です。さらに、やわらかさや粘りといった食感も際立っています。
新米への期待が高まってきました!
ただ、餅用や酒用も含めたお米の品種は実に900種類以上あり、ぼくたちの食卓に並ぶお米の品種は300種類以上あると聞きます。その中からおいしい新米を選ぶ秘訣はあるのでしょうか?

単一品種やブレンド米などの中からおいしい新米を見極めるには、次の3つの秘訣があるんです。ぜひ参考にしてみてください。
①いつ、どこで栽培された何という品種なのか、という基本的情報を確認すること。
②袋に入ったお米の粒を確認すること。
その際、粒が均一で、ふっくらとして厚みのある粒張り(りゅうばり)が良いものを選んでください。粒張りが良いお米はデンプン質が豊富で、甘みが強い証です。また、半透明でツヤのある粒であることもポイントです。
③品種特性を知り、自分の嗜好に合ったお米を選ぶこと。
例えば、やわらかく粘りの強いお米を好むなら「コシヒカリ」、粘りよりも弾力を好むなら「つや姫」「ひとめぼれ」「あきたこまち」というように、品種によって特徴もさまざまです。お米それぞれの特徴を見極め、ぜひ好みのお米を選んでください。さらに、カレーライスや炊き込みご飯など、硬めに炊き上がるお米が適している料理もありますので、用途によってお米を選ぶことも大切です。
数ある新米の中から、自分好みのお米や、用途に合わせたお米を選ぶことは、ぼくたちの普段の食生活を見つめ直す良いきっかけになるかもしれませんね。
新米のおいしい「食べ方」とは?

「研ぐ」から「炊飯する」、「食べる」まで、新米をおいしくいただくために欠かせないポイントもありそうですね。まず、「研ぐ」ときのポイントから教えてください。

私はいつも、「お米の顔を見て研いでください」ということをお伝えしているのですが、新米、古米の様子を見て研ぎ方を変えることが大切です。特に、新米は「やさしく研ぐ」ことが基本。古米に比べやわらかい新米は、強く力を入れて研ぐと粒が崩れてしまうからです。
また、1回目の水は、表面の汚れやぬかをさっと落とすだけという理由で素早く捨てるのが鉄則です。その後、水を替えながら2〜3度やさしく研いでください。
肝心なことは「やさしく研ぐ」ということですね。では、「炊飯」のポイントはどのようなことでしょうか?

炊飯時の水量を、お米1に対し1.1程度に控えることですね。新米は吸水力が高いので、通常の1対1.2から若干減らしましょう。また、風味豊かな米油を加えることにより、炊き上がりのツヤや香りが一層際立ちます(米3合に小さじ1程度)。
炊飯ジャーや土鍋、ガス釜や羽釜など色々な炊飯器具がありますが、器具選びで重要なことは、弱火から強火まで火力を調整できることと、一方向からだけではなく器具全体からお米に火力が伝わること、また、糊化が完全に進むために圧力を加えることです。直火が良いのはもちろんですが、近頃の炊飯ジャーは炊飯のコースが選べる機能を搭載しているものもありますので、充分おいしいご飯を炊くことができます。
さらに、炊き上がりの際にはしゃもじを使って天地返しをしてください。ふっくらとやさしく混ぜることで、上部、下部、内側、側面など不均一な炊き上がりを均一に整えることができます。併せて、ご飯の表面に付いた水蒸気を適度に逃す効果もあります。
おいしく炊き上がったら、ついに実食ですね!大坪先生おすすめの新米の食べ方を教えてください。

まずは、ぜひ「白ごはん」のまま召し上がっていただきたいですね。新米のおいしさを思う存分味わえるはずです。
次に「おにぎり」。大切なのは、空気をはらむようにふっくらとやさしく握ることです。お味噌や麹、お魚など、お住まいの地域のおいしい食材と一緒に楽しんでみてください。
それから「お粥」もおすすめです。白さ、香り、味わいなどすべてがおいしさを引き立ててくれます。
最後に、新米の「発芽玄米」も試していただきたいですね。玄米を発芽させることで、酵素の働きが活性化し、機能性成分であるGABA(ギャバ)が多く生成されます。GABAは高血圧や脂肪肝の予防、またリラックス効果も期待できる成分として注目されています。しかも、新米の発芽玄米は通常のものよりもやわらかく食べやすいのが特徴です。
お米は日本の宝、世界の宝

ここまでお話をお聞きすると、大坪先生も、ぼくたちと同じように新米の季節を楽しみにしているお一人のようですね。

もちろんです。新米を口にするたびに、「日本に生まれて良かった」と実感します。
毎日食べ続けることにより健康寿命の延伸も期待できるお米は、日本の宝であり、世界の宝でもあります。しかも、飽きのこないおいしさを持ち、パンや麺などの加工品の原料としても幅広く活用できます。
さらに水田は食糧生産の場であると同時に、洪水防止や地下水の保水保全にも役立っているのですよ。
ぼくも、日本に生まれて良かったと改めて感じています。お米はぼくたちの宝物ですね。

2013年に和食がユネスコ無形文化遺産に登録されましたが、その要となる「お米」を通じて、私たちは日本で育まれた稲作文化や食の歴史に思いを馳せることができます。なかでも「新米」は、四季のある日本で、秋の訪れを感じさせてくれる特別な存在です。ぜひ、おいしく食べていただきたいですね。
先生のお話をお聞きして、お米がますます好きになりました。そして、新米をいただくのが楽しみになりました!
春先から、農家さんが丹精込めて育ててきたお米。農家さんの姿を思い浮かべながら食べたいと思います。大坪先生、ありがとうございました。
こちらの記事もおすすめ

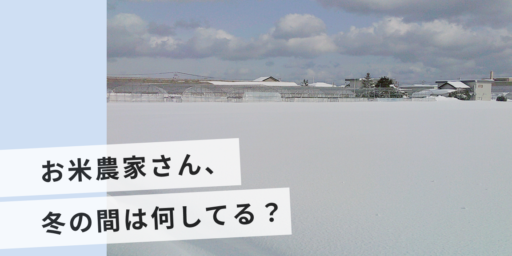



こんにちは。「新米」のラベルが貼られたお米が店頭に並ぶ時期になると、ぼくがいつも気になるのは「新米」と「古米」の違いです。
収穫したばかりのお米を「新米」、収穫から時間が経ったものを「古米」と呼ぶのでは?と考えているのですが、それぞれ定義があるのでしょうか?