静寂の中で味わう「黙食」には、ごはんがもっとおいしくなる効果がある?

食事中に黙ってごはんを味わう黙食。
コロナ禍で広く認知されましたが昔からあった言葉で、無言で食事に取り組むことで五感を研ぎ澄ませ、食事そのものに集中する意味合いがあります。
仏教の禅宗では食事は修行の一環であり、黙って食べるのが作法となっています。
修行の黙食から私たちが学べることはあるのでしょうか。
そこで曹洞宗の僧侶であり駒澤大学の教授として禅学科で教える晴山俊英さんに、
仏教に伝わる黙食の教えや、私たちが黙食を行うことで得られることについてお話を伺いました。
お話を聞かせてくれた人
晴山 俊英(はれやま しゅんえい) 先生
駒澤大学仏教学部禅学科教授。曹洞宗の僧侶の家庭に生まれ、駒澤大学では大学院まで進学し、修士(文学)過程を修了。その後指導者となり2001年より教授として駒澤大学で坐禅や仏教学入門など、授業を行う。
著書に『道元さまが教えてくれた心のコンパス「正法眼蔵随聞記」に学ぶ』 1・2 (曹洞宗宗務庁刊)などがある。

聞き手: ソラミドごはんくん
ごはんが大好き!
ちょっぴりヒツジに似たごはんの妖精。好奇心旺盛で、ごはんのことなら何でも知りたい!聞きたい!見てみたい!と思っている。

仏教では食べることも修行のひとつ
そうですか。昨今世の中でいわれる黙食と禅宗の黙食は同じではありませんが、禅宗の考えで現代の黙食に役に立ちそうなこともあります。今回はそれについてお話していきましょう。
よろしくお願いします!
まず、曹洞宗の修行生活ではお坊さん自身が食事を作って出しますが、作る方にも食べる方にも作法があります。
食べる方でいえばしゃべらないのはもちろんですが、極力音を立てないようにするとか、最後は鉢刷(はっせつ、20cm程度の板の先に布を巻いた道具)で器をぬぐって食べてきれいにするとか、皆が食べ終わるタイミングを合わせるとか、共同生活ゆえの作法も多いですね。
細かい決まりがあるんですね。仏教における黙食の歴史はわかっているのでしょうか?
黙食がいつ、どうやってできたというようなことがきちんと残っているわけではありません。ただ、仏教に関係する書物の中で黙食に通じる部分があるので紹介しましょう。

戒律に見える黙食や禅宗における食事マナー
探してみたところ、2点ほど黙食に通じるものを見つけました。長くなってしまうので簡単に説明しますね。
戒律(ルール)について書いた『摩訶僧祇律(まかそうぎりつ)』というものがあります。東晋時代(317-420年)の中国大陸で翻訳された戒律文献でして、ここに6人の僧侶の話があります。僧侶たちは在家信者(出家せずに仏教に帰依する人のこと)から食事を提供されているのですが、この6人はその食事を口に入れたまましゃべり、まるでラクダや牛など、動物のようだと悪い評判になります。その話を別の僧侶から聞いた釈尊(=ブッダ)は6人を呼んでそれが事実だと確認すると、「今日より以後、食べ物を口に入れたまま話をしてはいけない」と言ったそうです。
これが黙食の起源ですか? ここにはどんな意味が込められているんでしょう?
厳密には起源かどうかはわかりませんが、少なくとも下品なことをせず黙って食べましょう、食事マナーをちゃんとしましょう、とルールを決めたということなんですね。食と真剣に向き合い、同席する人への配慮をしなさいと求めている内容です。
そんなに昔からマナー感覚が変わらないというのは興味深いです!
本当ですね。また、曹洞宗の開祖である道元禅師(1200-1253)がまとめた『赴粥飯法(ふしゅくはんぽう)』というものがあります。「赴」がごはん、「粥」はおかゆの意味です。食事の作法の本なのですが、そこに食事の前に想像しなさいという意味の「五観の偈(げ)」という5つの唱え文句があります。
食事をいただく際に食事にかかった手間や誰が作ったのかを想像してみなさい、自分の行いの良し悪しを点検して、食事の供養に値するかを考えなさい、もっともっとと望んだり、怒ったり、無知であったりしてはいけない……というような内容です。
これは曹洞宗系の幼稚園や小学校などで給食を食べるときに今も唱えられているものです。
これもさっきの『摩訶僧祇律』にあったように、食事と真剣に向き合いなさいとか、周囲に意識を向けなさいとする教えですね。ここにも黙食に関することが書かれているんですか?
『赴粥飯法』の後半には食事の際の注意事項が列記されています。
例えば食器は手に持って口に近づけて食べるとか、隣をのぞいて量が多いとか、おいしそうだと比較しないとか、肘をつかないとか。「音を立てて食べない」「大量に口の中に入れない」というのが黙食につながるもののように思います。
ほかにも息を吹きかけない、お茶やお湯で口をすすがないなど、他人に不快感や違和感を与えないような配慮をして食べなさい、という注意が続きます。
今でも当たり前のようなマナーばかりですが、道元禅師の頃には形になって、修行の場で実践されていたんですね。
黙食の効果とは。しっかり味わうことでごはんが何倍もおいしくなる?
仏教の教えや戒律の中で黙食に関するものを紹介しました。ここから読み取れるのは、食と正面から向き合い、他人へ配慮するひとつの決まり、方法として黙食があるということです。
しゃべらずに食べるというだけではなくて、好き勝手に食べて不快感を与えないように、という意識や、食べることに対する感謝の気持ちを感じます。
では、実際に黙食をすることの効果にはどんなものがあると先生は考えられますか?
いくつかあると思います。ほかのことに気を散らさずに食事に集中することで良いのは、より味覚が研ぎ澄まされるということです。
私は今でも坐禅会に行きますが、修行道場で出る食事というのは精進料理なので基本的に淡白で、おかずも少ないです。ごはんのおかわりはできますが、それでも大事に大事に食べて何度も咀嚼します。そうするとご飯がびっくりするくらい美味しく感じるようになるんですよ。

そんなにおいしく感じるんですか?
そうなんです。やはり坐禅などの修行をしていく中で感覚が研ぎ澄まされているせいでしょう。飲み込むのがもったいないな、と思うくらいおいしいですよ。
ぼくもぜひ一度経験してみたいです。
また、たくあんなどでも極力音がしないような食べ方を習得していくし、周囲の様子に気を配り、人に合わせて全員が同じタイミングで食べ終わるよう調節するなどしていきます。修行道場では食べ終わった後の器は、鉢刷でぬぐってきれいにし、洗い物の手間を減らします。それが身につくと、普段の食事の際にも、たくあんを一切れ残しておいて、食後にお茶かお湯か水かを器に少し入れ、そのたくあんで器をぬぐうようになります。
こうやっているうちに自然と他人に配慮し、迷惑をかけない食べ方を意識していくのですが、こうしたことは日常生活でも気遣いや気配りができることにつながりますし、黙食の効果といえます。
ごはんがおいしくなり、周囲に気配りができるようになるなんて、とてもいいことですね。食事が修行であるというのは納得です!
食に集中することで「もったいない」の意識が生まれれば、残すこともなくなりフードロスや環境への意識も高まるかもしれません。私の考えなので、これが黙食の効果だと決まっているわけではありません。でも食事を通して人を気遣う気持ちを育むことができるし、またごはんがおいしく感じられるのは確かなことだと思います。
集中力や思いやりを育む現代の人に合わせた黙食
修行をしていく中での黙食のよさというものはよくわかりました。でもぼくたちは修行僧ではありません。今の時代の人たちの黙食ではどんなことを意識すれば良いと思いますか?
全くの無言で食事に集中することができれば修行道場のような感覚は得られると思いますが、それはやはりちょっと難しいですよね。
「今日の味つけはいいね」とかそうした会話はあっても全然いいと思います。じゃあ何ができるかなと考えると、食事にどうやって集中するかということでしょうか。そのひとつがテレビをつけない、スマートフォンを見ないでごはんをいただくというやり方だと思います。
現代では家族でみんながそろって食卓を囲むということが昔よりは少なくなっていると思います。でも家族で食事をしようというのであれば、やはり食べることのみに集中する時間を作ることが必要だと私は思います。

食事の時にテレビを見ている家は多いと思います。スマートフォンを見ながら食べる人も、いまでは当たり前にいる時代になりました。
テレビを見ながら食事をするようになったのは私の親世代ぐらいからだと思います。今はスマートフォンも加わりましたが、誰かと食事をしている時に他のことをするのは気遣いが失われている状態ですし、散漫になって集中力もありません。
そうすると食事もただ食べている状態になって、集中していたら感じられるおいしさを感じられなくなっているかもしれないわけですね。
そのとおりです。食事を作った人からしてもそれはやはり悲しいのではないでしょうか?
惣菜など買ってきたものを食卓に出すとしても、「ご馳走」というのは走り回るという意味ですから、頑張って集めてきたものなんですよね。食事に集中していないということは、そうした労力をかけて用意されたものだという想像力が働いていないことになりますから。
先ほどの『赴粥飯法』の「五観の偈」にあった、どうやってこのごはんが食卓に並んでいるのか、想像してみなさいという部分ですね。
そうです。時代の流れとともに価値観も変わってきています。
でも完璧に実践できなくても最低でもこうあるべきだと理解していて守れていないのと、まったく知らないのではぜんぜん違います。知っていれば他人に配慮しよう、食事に感謝しようと自然になっていきますし、それは食育にも役立つと思います。
先生に教えていただいたことを少しでも意識するだけで、毎回のごはんがおいしくなったり、他者への思いやりが芽生えたりして、ごはんの時間が充実しそうな気がします。
ぼくもごはんがあることに感謝して、黙ってたくさん噛んでおいしさを味わっていきたいと思います。晴山先生、ありがとうございました。
こちらの記事もおすすめ
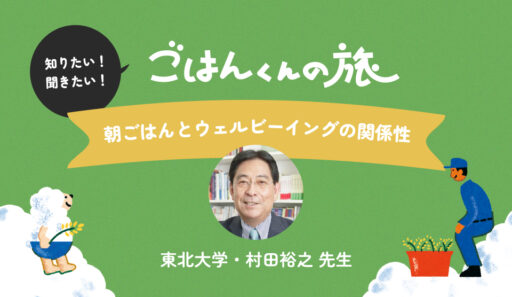


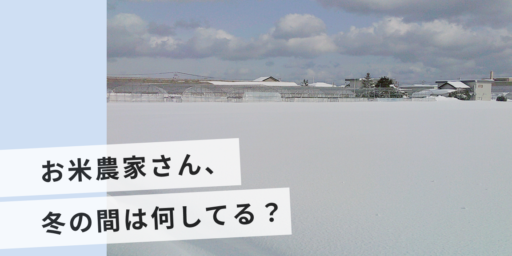

こんにちは。黙食は食べることに集中することで五感をフル活用できるということで、注目されている食事スタイルのひとつですよね。ごはんのよさを広めたいと思っているぼくもとても気になっています。
禅宗では食事も修行の一環で、黙って食べる作法があると聞きました。どのような経緯でそのような作法が生まれたのか知りたいです。