令和の米騒動を専門家が解説! お米を取り巻く経済の現状と、2025年米不足の予測とは

2024年の秋以降、スーパーの売り場からお米が消えたり
買い占めや価格が高騰したりして、私たちのごはんに危機的状況がもたらされました。
その騒ぎからしばらく経過し、お米が手に入るようになりましたが、
価格は高止まりしていたり、2025年の初めごろには早くもお米の在庫状況が危ぶまれているといった話も出てきています。
“令和の米騒動”ともいわれたこの混乱はなぜ起こってしまったのでしょうか。
そしてこの先、美味しいごはんを安心して食べられる世の中は続いていくのか、
消費者としては気にせずにはいられません。
農業経済の専門家・小川真如先生にソラミドごはんくんがお話を聞き
2024年から現在にかけて何が起こっていて、この先はどうなるのか、わかりやすく紐解いてもらいました。
お話を聞かせてくれた人
小川真如(おがわ まさゆき)先生
宇都宮大学学術院(農学部)農業経済科 助教(大学院地域創生科学研究科兼任)。東京農工大学大学院助教。
農業経済学を専門に、一般財団法人農政調査委員会の専門調査員や、公益財団法人日本農業研究所の客員研究員など、さまざまに活動。個人でも農業関係者へのインタビューを行い、情報を収集している。
日本のコメ問題に関する著書に『日本のコメ問題』(中公新書・2022年)、『現代日本農業論考』(春風社・2022年)、『水田フル活用の統計データブック』(三恵社・2021年)などがある。

聞き手: ソラミドごはんくん
ごはんが大好き!
ちょっぴりヒツジに似たごはんの妖精。好奇心旺盛で、ごはんのことなら何でも知りたい!聞きたい!見てみたい!と思っている。

前回、小川先生にお話を聞いた記事はこちら

需要と供給バランスの崩れや社会の動揺が生んだ“令和の米騒動”
2024年のコメ不足は供給と需要、両方の要因がありました。
供給面では2022年からコメの品薄感が少しありました。そして決定的な出来事として、2023年の猛暑で高温障害が起き、全国的にコメの品質が落ちてしまいました。
コメの等級は4区分ありますが、中でも日本人が大好きな人気のコシヒカリは、新潟県産の場合、1等米比率が平年の75.3%から、4.9%にまで落ちたんです。2023年がそんな状況だったので、当然2024年に新米を収穫するまでの間は質の良いコメが少なかったのは確かです。
また、選別時にふるいにかけると下に落ちたものを「ふるい下米」と言いますが、これが2023年度産は51万トンから32万トンに減ってもいます。こうしたコメは低価格の食用米やせんべいなどの米菓、ビールなどの加工用原料になりますが、これも激減だったんです。
低価格米や原料用のものもそんなに少なかったんですね。
そして需要面だと、農林水産省の予想以上に需要がありました。
理由としては物価高が大きいと思います。主食ではウクライナ危機などにより小麦の高騰がパンや麺などの値上がりにつながっています。そうすると、あまり大きく値段が動かずにいたコメが割安に感じられて、需要が伸びやすい状況になっていたところがあります。
外食産業の回復傾向やインバウンドの増加もそこに加わり、コメを欲しがるところが想定以上に増えたんです。
作る方は不作で、使う方が想定以上に欲しがったことでバランスが崩れてしまった、と。
2023年のコメの出来が悪いとその年の秋にわかってから、関係業者は早めの確保に動いていたんですよ。
でも2024年の新米が出回る直前の8月に南海トラフ巨大地震の臨時情報が出たり、大型の台風がノロノロ居座って、全国の広い範囲で食料の備蓄意識が高まりました。そうしたこともすべてが重なって、メディアいわく“令和の米騒動”として大きく報道され、消費者も焦って買いに走り、いわゆる“スーパーのコメ”がなくなってしまいました。

2025年度のコメの需給予測は高難度
うーん、2024年はいろんなことが重なって、ぼくたち消費者もそうした情報に反応しすぎてしまったことで米不足に拍車をかけてしまったんですね。
その後、新米が出てきて店頭では在庫が回復し、2025年に入った今も家庭用のお米はスーパーでも普通に買えるようになりました。でも価格は高いままか、むしろ値上がったような感覚です。今はどんな状況だといえますか?
日本ではコメを基本的に1年に一度しか収穫しません。一度足りなくなると落ち着くには数年かかると思ってください。
また、2024年の新米の時期が過ぎましたが、ここから2025年の新米が出るまでの間というのは、業者は2024年産米と2023年産米を組み合わせながら使っていく期間なんです。でも一度品薄になったことで、スーパーなどでは高くても仕入れたい状況ですね。これまで取引をしたことのない業者から問い合わせが入ってきた生産者さんも多かったようです。
そして2025年序盤の今は古米(2023年度産)も少ないですから、値段が落ちずにいるというところです。
ここ数年の民間のコメ在庫量は以下になります。2024年は古米が極端に少ないのがわかると思います。
2022年度11月末 330万トン(新米263万トン/1年古米49トン)
2023年度11月末 303万トン(新米254万トン/1年古米36トン)
2024年度11月末 260万トン(新米234万トン/1年古米18トン)
資料:農林水産省「米穀の取引に関する報告」より、主な出荷販売業者・団体の在庫量
わっ、本当ですね。2024年夏のコメの品薄がこんなふうに影響しているんですね。
消費者の買い方も変わってきていて、品薄をきっかけに直接生産者さんから買う人は増えたと思います。
だからこそどこの生産者がどれだけコメを持っているか、全体を把握しにくくなってもいます。マスコミが不安感を煽った影響もあって、値段が高止まりしているのもあるでしょう。
1993年の平成の米騒動といわれる冷害のときは、夏頃の値上がりを狙って生産者側が普段より少し多めにコメを手元に残していたこともありました。
でも今回は収穫が始まれば落ち着くだろうと思っていた人も多く、早めに売り買いを進めて在庫を抱えていません。つまりあとから出てくる在庫もないし、どこにコメがあるか全国的に把握もしにくいので業者も苦労していると思います。
現在は足りているとはいえ、古米の量が少ないことやコメの売り方も変わってきて、業者さんも買付けは昔ほど簡単ではない様子がうかがえます。
じゃあ、2025年はどうなっていくと先生は考えますか?
農家や業者、研究者の人たちとも話すんですが、2025年のコメ予想はかなり難しいですね。
コメは春に作付面積が決まり、夏に向けて育ち具合が見えてようやく全体が見通せるものですから。私個人としては、2025年は作付面積が増え、生育が順調だった場合は秋に供給が過剰になると予想しています。そして高値で買い集めた2024年度産も1年経てば古米になってしまいますから次第に商品価値が落ちていき、販売価格は2026年春頃に落ち着いて、6月頃から下がるか、値下げ競争になるかもしれません。
ただ、国の見通しではそう楽観的ではなく、2025年6月の民間在庫量は今年に次ぐ低水準としています。需要が上回れば容易にコメ不足になるかもしれません。政府備蓄米がどのように影響するかも注目されます。
先生の予測と国の考えも違うように、読めないところが多いんですね。
それだけではなくて、今後も異常気象やそれこそ南海トラフ巨大地震の臨時情報のようなものが再び出たら、状況がどんどん変わっていくということですよね。
そうですね。
生育が順調だと価格が下るかもしれない、ということですが、今はいろんな物価が上がり、生産者さんも経費がかかっていると思います。それでも価格は下がるのでしょうか?
確かに全体的な物価高は進んでいるので、ある程度高い状態を維持して、物価上昇に合わせた価格で推移すると思います。
下がっても去年や一昨年のような価格になるかといえば、あまり考えにくいですね。

先は簡単には見通せないからこそ、知識を持って行動しよう
不安定な要素が多くて、この先農家さんやコメ作りはどうなっていくのか、そしてぼくたちはごはんを食べ続けられるのだろうかと少し不安になります。
農家の多くは家族経営で価格交渉力が低く、例えば企業相手に高値で売って稼ぐということは難しいでしょう。だから国としては継続的にコメ作りができるような仕組みづくりを今模索している段階です。
2024年6月に食料・農業・農村基本法が改正され、今はそれに基づいた食料・農業・農村基本計画を立てている段階なんですが、今後20年程度を見据えて課題を整理したうえで、5年間の具体的な計画が示されます。
コメの価格が高騰すると消費者は大変ですが、農家も安いままではやっていけないですから、どのような方法を取っていくか、しっかり考えなければいけません。
日本人にとってごはんというとお米だし主食なので、足りないと国が動いてくれるのでは、という感覚があります。
でも法的には自由に売り買いするほかの農作物と同じということですもんね。だけどやっぱり主食であるお米は特別な食べ物なので、常に安定した価格で手に入れたいと、食べる側としては思ってしまいます。
自由に売り買いできるようになったことで産地間競争が起こり、新たな品種開発が進んできたといういい面はあります。
でも一方でお米が手に入らなくてもある意味自己責任ですよ、というデメリットが露呈したのが昨年だったと思います。
お米を食べることが減っているといわれているのに、いろいろな要因が絡んでいる現在はコメ集めが大変だなんて。なんだか不思議な気がしますね。
食べる量についてもまだ未知数なところはありますね。
減っていくとはいわれていますが、昨年は一気に需要が増えました。これは単に一時的な出来事なのか、それとも需要は今後も減り続けるのか、不透明でもあるんです。何を食べるかはそのときの社会状況にも左右されますしね。
それに、日本人が好きなコシヒカリは高温に弱いので、この先は品種を変えていく動きも加速するのではないかと思います。そうしたときにコシヒカリのように好んで食べてもらえないと、消費量は減るかもしれないですね。
生産者さんと話をすると、基本的に高温に弱いコシヒカリを別の高温耐性品種に変えていこうとする人もいれば、そうやって品種を変える農家が増えるとコシヒカリが品薄になり高く売れるので、作り続けたいという人もいます。生産者さんも経営戦略を考えつつ、稲作をしていく時代です。
なんにせよ、これまでとは違う目線を持ってお米を選んだり、食べたりしていくことが大事ですね。
消費者の方も軽い知識でいいので、理由を知っていただくのは大事だと思います。
卵なら鳥インフルエンザが流行っているとか、ウクライナ危機で餌の値段が高くてとか、高値の原因はニュースで目にするでしょう?
なんとなくの知識で十分なので、コメもコシヒカリは暑さに弱いらしいと知っていれば、他の品種も食べてみようとか、納得して別のものを手にしてもらえると思うんです。それがきっかけになり、いろんな品種をそのときの状況に応じて選んで食べていく人が増えれば、今回のような騒動は起きないと思います。
ニュースの不安なところだけに目を奪われないで、最低限の知識は持つことで冷静になれますよね。ぼくも視野を広げてごはんを食べていきたいと思います。
小川先生、解説していただいてありがとうございました。
こちらの記事もおすすめ


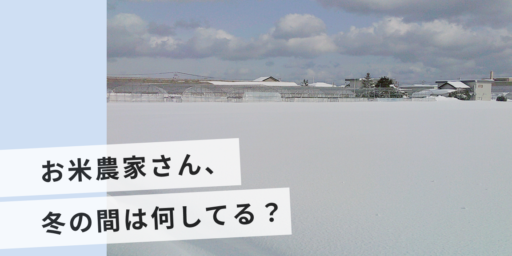


小川先生こんにちは。
前回は今の日本におけるコメ状況を解説していただきありがとうございました。今回は米不足で混乱した2024年のことや現在のこと、またこの先どうなっていきそうなのか、わかる範囲で教えていただけたらと思っています。
まず、2024年の夏から秋にかけて起こった米不足とその混乱原因を改めて確認したいです。
このときは家庭用のお米がスーパーなどの店頭から品切れになる騒ぎになりました。前回のお話では国内のお米は短期需要で作っていて足りているということだったのになぜですか?