悠久の歴史と食文化が生んだ、京都のお米「京式部」─京都ならではのお米の魅力とは?─

その名に古都の奥ゆかしさを宿す、京都のオリジナル米「京式部」。
開発の原動力となったのは、地球温暖化による品質低下への危機感と、京料理にふさわしいお米へのこだわりです。
京都府と国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が4年をかけて取り組んだ開発プロジェクトには、生産者はもちろん、京料理人をはじめとする食の専門家たちの思いが込められています。
今回は、新たな京都の味として注目を集めている「京式部」の開発経緯やそのおいしさについて、京都府農林水産技術センター農林センター栽培技術開発部の尾崎耕二さんと香月彩花さんに詳しくお話を伺いました。
「京式部」についてお話を聞かせてくれた人
尾崎耕二さん
京都府農林水産技術センター農林センター栽培技術開発部主任研究員。水稲・豆類の栽培技術開発を担当し、これまでに、京都府独自の酒造好適米品種「祝2号」の育成や酒造用原料米「京の輝き」の選抜、「コシヒカリ」の生育診断、エダマメの機械化栽培等の技術開発に従事。
-768x1024.jpg)
香月彩花さん
京都府農林水産技術センター農林センター栽培技術開発部技師。水稲・麦類の栽培技術開発を担当。水稲においては、「京式部」の生育診断や栽培試験を行う。
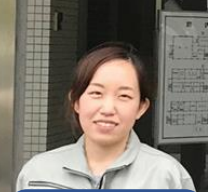
生産者の声が動かした、京都独自のお米作り

全国の府県で続々と登場しているブランド米。京都府でも「京都らしいお米を作ろう」との機運が高まり、2017年から新品種の開発がスタートしました。それから4年の歳月を要して完成したお米が、「京式部」です。開発の背景には、地球温暖化の影響によるお米の品質低下という、生産者にとって深刻な問題があったといいます。
京都府は、日本海側の北部、中央の山間部、京都市を含む南部と、南北に広がる府域。全国的にも人気が高い京野菜をはじめ、さまざまな農作物が栽培されていますが、なかでも水田の割合は耕作地全体の8割を占めています。 主に作られているのは、「コシヒカリ」「キヌヒカリ」「ヒノヒカリ」の3種。ですが、いずれも古くからある銘柄で、近年の猛暑下では品質保持が難しい状況になっていたとか。特に一等米の割合は年々減少し、府には生産者からの「暑さに強いお米を開発してほしい」という要望が多く寄せられていたそうです。
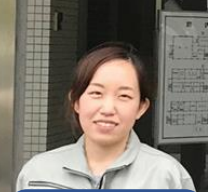
京都独自というのは、京料理と調和するという意味も含まれています。古くからの食文化が根付く京都の新たなお米として、欠かせない要素でした。
食のプロとともに育てた「京式部」。京の味にふさわしいお米とは?

「暑い夏でも育つお米」、「京都独自の品種」という生産者からの要望。それらに応えようとスタートした新品種の開発は、京都府と国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下、農研機構)との共同研究で進められました。 まずは、農研機構の北陸研究センターから提供された、11の系統(※1)のお米をコシヒカリと比較しながら栽培。そのなかから、段階的に京都の環境に適したお米を選抜していく作業が行われました。
(※1)系統:遺伝的に特定の特徴を持つ稲の集団のことで、系統の中でも特に優れたものが選抜されて品種になる。
.jpg)
稲が育つ様子を観察しながら、風雨や台風などの悪天候でも倒れにくく、生産者が栽培しやすい稲を選んでいきました。そして同時に重視したのが、安定した収量が確保できることと、食味(※2)の良さだったんです。
(※2)食味:ごはんとして食べたときのおいしさ示し、甘み、粘り、やわらかさ、香り、ツヤなどで総合的に評価される指標。
京都独自であり、なおかつ京都らしさを体現するお米に欠かせないのが、食味の良さ。その実現に向けて、開発の初期段階から関わったのが京料理人やお米マイスターたちでした。食のプロフェッショナルによる評価を通じて、食味の確かさを裏付ける取り組みはさらに進みます。
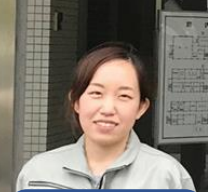
11系統のお米から5系統を選抜し、さらにそこから絞り込んでいったのですが、いずれの段階でも京料理人や米マイスターたちに実際に食べていただき、評価をもらいました。
独自の食文化が育まれてきた京都だからこそ、こだわってやまないおいしさ。ただそのこだわりの背景には、挑戦と失敗を何度も繰り返してきた、新品種開発においての教訓もあったそうです。
.jpg)
京都府はこれまでお米に限らず、様々な品目で品種開発に取り組んできましたが、デビューさせたものの需要が伸びないという事例があり、その要因の一つは、食味への評価が不十分だったことも考えられます。
だからこそ、今回は開発段階から食の専門家と連携し、納得できる味を追求したんです。
京料理を彩る「京式部」のやさしい甘みと美しさ
実際に「京式部」の評価につながったのは、程よい粘りと上品な甘み、そしてしっかりとした粒感。料理に寄り添いながらも主張しすぎない、「京都ならではのお米らしさ」です。京料理は素材の持ち味を活かす繊細な味付けが特徴。それを理解する京料理人やお米マイスターの意見はなによりも重視されたそうです。
そして、京都の気候や風土に適した品種として最終選抜まで残り、併せて食の専門家も認めた京都のオリジナル米がついに誕生しました。京料理店への限定提供から始まり、2021年には一般の生産者による栽培もスタート。京都府内のお米専門店や百貨店などでも販売が始まりました。
「京式部」の名は、世界最古の長編小説といわれる「源氏物語」の作者・紫式部にちなんで付けられたもの。その上品な響きからは、京都の長い歴史と、そこで育まれた文化の華やかさも感じます。
.jpg)
『京式部』は、実際の食味評価でも、コシヒカリを上回る点数を獲得しています。ただそれ以上に、食の専門家に認めていただいたことが、品質の良さの証です。『コシヒカリよりも味もツヤも、食感も良い』という感想をいただくこともあるんです。
私が実際に食べてみて感じるのは、程よい粘り。コシヒカリよりもあっさりしたお米が好きな人にはおすすめです。さらに、ほんのりとした甘みや旨みもあって、どんな料理にも合わせやすいと言われることも多いですね。京料理人たちからは、白いご飯そのままはもちろん、炊き込みご飯や丼、お茶漬けにも良いという声をいただいています。粘りが強すぎないため、お寿司のシャリにも良いとよく聞きます。
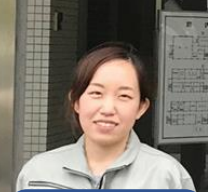
粒が大きくしっかりとしているのも特徴です。なにより、炊き上がりの白さとツヤは、他のお米と比べても群を抜いています。炊飯ジャーや土鍋など、どんな器具でも変わらぬおいしさに炊き上がるのも、このお米の品質が良いからだと感じます。
京都のお米を未来へつないでいくために

独自の食文化が受け継がれている京都で、料理人が認めるというプレミア感とともに、消費者の間でも徐々に評判になっている「京式部」。今では、地元のスーパーなどでも販売されているそうです。 ただ、開発当初から安心安全にこだわり、栽培方法を「特別栽培米」に限定していることが、生産拡大の壁になっていると尾崎さんは説明します。
.jpg)
特別栽培米は、農薬や化学肥料の使用量を慣行栽培の半分以下に抑える必要があります。そのため、栽培に踏み出せない生産者も少なくありません。ですので現時点では、作付面積は全体の1%ほどにとどまっています。ただ、安全なお米だからこそ、これまでよりも高い価格で販売できるというメリットもあるんです。
今後の普及をめざし、開発チームでは、より早い時期に田植えができる栽培技術の研究を進めているとのこと。実現すれば、既存の品種と合わせ栽培時期が広がり、より多くの収穫も見込めます。つまり、生産者にとっては収入増加も期待できるのです。
開発チームとして、さらなる研究と「京式部」の普及に取り組む尾崎さんと香月さん。最後に、お二人が思い描く「京式部」のこれからについてお聞きしました。
.jpg)
このお米の良い点をさらに磨きながら、同時に生産者に安心して栽培してもらえるような技術を確立したいですね。作付面積を広げ、安定した収量を確保できるように支援していくことが大切だと考えています。
そしてなによりも、できたお米を一般の消費者、特に子どもたちに食べてもらいたい。京都府全体で『京式部』を盛り上げていければと思っています。
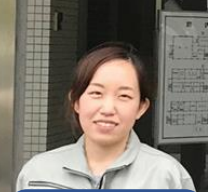
まずは、京都府内に普及させることが目標です。そのためには、生産者の声を聞き、育てやすい環境を整えること。それが私たちの役割だと考えています。
「京式部」開発に携わった尾崎さん、香月さんに取材してみて
「京式部」は、多くの人々の思いが形となった結晶です。気候変動というお米作りを揺るがす大きな課題と、京都ならではの食文化を支えたいという強いこだわり。その両方に向き合う尾崎さんと香月さんの言葉からは、決して諦めない研究者としての熱意を感じます。「京式部」が京都中の食卓へ、さらに全国の食卓へとどのように広がっていくのか。今後の成長が楽しみです。
取材・執筆: 福島和加子
ソラミドごはんでお取扱中の「京式部」


こちらの記事もおすすめ


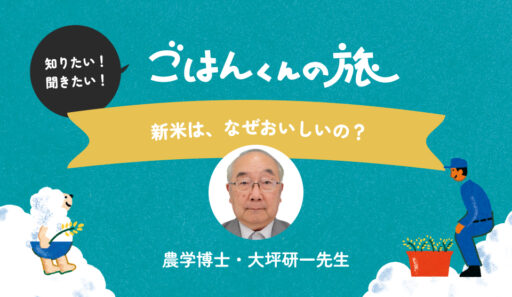


生産者からの声は切実でした。しかも、将来的にみても、夏の気温上昇は長く続くと予想され、高温に強い新品種の開発は急務だったんです。併せて、『京都独自の品種を作ってほしい』という要望もありました。