古来からの知恵「米麹」のチカラを毎日のごはんに取り入れ、健やかに

健康志向の高まりで、健康によいとされるさまざまな食品に注目が集まっています。
その一つが「米麹」。蒸したお米に麹菌を種付けし、繁殖・発酵させたもので、米味噌や甘酒、日本酒、塩麹、そして酢などをつくるときに使われます。
日本の食卓に欠かせないといえる米麹ですが、なんとここから取れるエキスにストレスを軽減させる働きがあるのだとか!
米麹を食生活に取り入れることでストレスが軽くなるとしたら、心と身体、両方にとってきっと良いことに違いありません。
ごはんとして食べるだけではなく、コメ由来の食品でお米の価値が高まるのもうれしいことです。
この研究をされ、論文を発表された新潟大学の准教授・岡本先生に、研究の内容や、米麹をめぐるいろんなお話を聞いてきました。
岡本圭一郎 先生
新潟大学 医歯学総合研究科 口腔生命科学専攻 摂食環境制御学 准教授
大学卒業後、歯科医師として歯科口腔外科の分野で臨床経験を積む。その後アメリカのブラウン大学医学部、ミネソタ大学歯学部などに学ぶ機会を得て、痛みとストレスの脳メカニズムに関する基礎研究活動に従事。帰国後は2015年より新潟大学に赴任。心理ストレスが誘発する歯科領域の慢性疼痛の脳メカニズムの解明や、生活習慣の工夫による制御法などを研究テーマにしている。新潟県という地域に関連し、日本酒や米麹、酒粕等に注目。ストレス軽減作用についての研究に注目が集まる。日本酒にかかわる文化的・科学的な幅広い分野を網羅する学問分野「日本酒学」の構築を行う新潟大学日本酒学センター協力教員も務める。

ソラミドごはんくん
ごはんが大好き!
ちょっぴりヒツジに似たごはんの妖精。好奇心旺盛で、ごはんのことなら何でも知りたい!聞きたい!見てみたい!と思っている。

慢性痛の研究から発展し、着目した米麹のパワー


よろしくお願いします。いやいや。私は食品や米麹の研究家じゃないんです。口腔外科、つまりは歯科医師で、今は歯学部の教員として歯学教育に携わっています。この分野で臨床や研究、そして学生にも指導をしています。歯科臨床では痛みとストレスというのはとても身近なものなので、もともと興味を持っていましたが、実はどのような関係性があるのか、あまり分かっていない分野なんです。ストレスとか痛みと脳メカニズムに科学的に興味を覚えて研究をするようになりました。
健康に良いものを探して興味を持ったのではなく、痛みとストレスの関係を探っていくうちに、米麹にたどりつかれたんですね。

そうなんです。痛みの治療というのは、普通に考えると薬の開発っていうのがわかりやすいアウトプットですよね。でも頭痛とかお腹が痛い、関節が痛い、というようないわゆる慢性痛は薬でどうこうするものではなく、治療が難しいんです。治る人もいるけれど、何となく我慢して治らない人の方が多い。
確かに病気ではないけれど、どこか痛いということはよくありますね。でも痛みがあるからストレスになります。

そうそう。通常、痛みというのは怪我をしたから痛いとか、明確な理由があって発生するものです。でも慢性痛は怪我をしていなくてもなんだか痛いという状態です。天気が悪かったら頭が痛いとか、関節が痛いとかありますよね? でも原因がはっきりしないから、薬による治療が難しいんです。結局、こうした痛みは「刺激がないのに痛みが起こっている」状態で、脳の機能がおかしいということになっています。それをどうしたらいいかと考えたときに、薬というより生活習慣を見直そうという機運が高まっていて、生活習慣や食生活のような、そういった基本的なところをやっていこうというのが世界的な対処法として広がってきているんです。
そこから米麹エキスのような、食べ物に着目されたんですね。

私はアメリカで痛みやストレスと脳のメカニズムに関する研究をしていたのですが、帰国後は新潟大学にお世話になることになりました。新潟というとやはり米どころです。地域創生に取り組もうという大学の機運もあり、新潟で地域に貢献できる活動はなんだろうと考えたらやはりお米ですよね。それに人はストレス解消にお酒を飲んだりするので、そういう研究がいいんじゃないかと思って最初は日本酒をテーマにしたところからはじめました。
米麹に含まれるエルゴチオネインをラットに与えて実験
日本酒からスタートした研究だったんですね。米麹エキスがストレスを軽減するのは、どういうことなのか、研究成果についてぜひ詳しく教えてください。

お酒を飲んだら気分がよくなるとか、痛みがやわらぐというのは感覚としてありますよね。それを確かめるために最初は日本酒、次は酒粕でラットによる実験を行い、どちらもストレス軽減効果が見られたのですが、この二つはアルコールを含んでいます。そのため、アルコールを含む食品の大量摂取を推奨しているような誤解を与えてはいけないということや、地元の酒造メーカーさんから甘酒に関しても調べてくれないかというご依頼をいただいたりして、現在の米麹を使った研究にたどりつきました。
調べると酒粕のアルコール分は8%ぐらい、米麹からつくられた甘酒はアルコールが0%なんですね。甘酒は酒粕よりも少し手軽で、誰でも摂取しやすそうです。最近は米麹飲料や調味料もたくさん発売されていますね。米麹の中の具体的にどんな成分が良いというものはあるのでしょうか?

酒粕もそうですが、米麹からつくられる甘酒に含まれている成分はものすごくたくさんあって、美肌やストレス軽減、腸内環境の改善、炎症抑制など、さまざまな健康に良い効果があると知られています。私たちは最初に米麹をラットに与えて実験して効果が見られたので、その中でも強い抗酸化作用を有するエルゴチオネインという物質に注目しました。抗酸化作用は活性酸素による体へのダメージを軽減、つまり、ストレスを軽減するような役割があって、酒粕や甘酒にはたくさん含まれているんです。これをラットに投与すれば、不安行動とか痛みの増大の軽減を観察できるのではないかと思いました。
エルゴチオネイン以外に候補物質はあったのでしょうか?

酒粕や甘酒、米麹などは食品関係の分野で活発に成分分析がされていて、ありとあらゆる栄養成分が入っていることがわかっています。だから、それぞれが全部健康に作用しており、「どの成分が直接キーになっているか」ということではないと思っています。ただエルゴチオネインはストレスを軽減するような役割を持っているんです。毎日飲み続けるとある程度体に溜まる物質でもあるので、積み重ねによって少しずつ体のいろんな機能を調節しているんじゃないかと考えました。たくさんの身体に良い成分の中でも、エルゴチオネインにポイントを絞って調べてみたのはそういう理由です。
ラット実験ではそれが示されたんですね? どんな結果だったか教えてください。

まず、ストレス状態のラットの様子を見てみました。人もそうですが、広い場所では通常は端に固まります。でも好奇心が強い動物なので、そのうち中央に出てくることもあるんです。その中央における滞在記録がどれくらいかを調べました。ストレス状態で気分が滅入っているラットは真ん中のエリアにはほぼ滞在しなくなりましたが、米麹エキス、またはエルゴチオネインを与えたラットは滞在する時間が長くなりました。また、ボックスで暗い部屋と明るい部屋を用意してつなげ、そこにラットを入れます。ストレス状態になると暗い部屋にとどまる時間が長くなるんですが、米麹エキスなどを投与してストレスを解消してやると、明るい部屋に滞在する時間が長くなるという結果になりました。
へえ〜! 米麹エキスやエルゴチオネインを投与することでそんな違いがはっきり出るんですね。

食品として成分分析したところ、健康にいいものが含まれているという報告はたくさんあります。でもストレス状態からの変化を見るという実験はこれまでされてきた例が見当たらないので、これは新しいというか、やはりそうだったのか、といえる結果を示せたと思います。
日常生活においては食生活で健康のベースをつくろう

実験結果を見ると、エルゴチオネインだけを摂取するのでも良いのかなと思ったりしますが、そんなことは可能なのでしょうか?

そうですねえ、多分甘酒を1日何リットルみたいなお話になるので、非現実的だと思います。たとえ飲めたとしても、糖分をかなり摂取することになるので良くないですね。そもそもこれはエルゴチオネインそのものにストレスを緩和する効果はあるという実験結果で、米麹にはそういうものが含まれているというのを示しただけです。基本的には日常の食生活をちゃんとすることが第一でしょう。米麹や甘酒などを日常的に摂取することで、たとえ自覚するような効果はなくても、健康のベースラインが維持されているというのが私の考えです。
確かにそうですね。おいしいごはんをちゃんと食べることで健康なことが一番だと思います。でも米麹や発酵食品などは身体にいいよといわれているけど、このように科学的に明らかになることで、もっと飲んでみよう、食べてみようとなるといいですね。

我々の研究のように、米麹の中のどの成分が生体機能にどんな影響を与えるかという研究はこれまでほとんどされてきていないんです。だから米麹や酒粕などのコメ由来の食品にもっと注目してもらうきっかけになるといいですね。
えっ、そうだったんですか? 歴史が古くて研究され尽くされていそうなのに意外です。

歴史が古いことが理由なんですよ。米麹なんかそれこそ、古事記のような文献にも出てくるほどで、何も調べなくても食品としては安全性が高いと思われている状態です。だから健康に良いものだけど、意外と細かく調べられてはこなかったんです。ただ、近年になって機能性食品というものができてきて、食品に関しても科学的に根拠を示していこうという風潮になっていると思います。疾患の面でも、たとえばうつ病は神経細胞の酸化が関係しています。だとするとエルゴチオネインが入っている甘酒を飲めばうつ病が治るという仮説が成立します。それが本当かどうか調べよう、というのが最近の流れですね。
だとしたらこれから明らかになってくることも多そうですね。ちなみに、岡本先生は日常的に米麹を摂取していたり、体調の変化を感じるような経験はありましたか?

それが、もともと慢性痛などもないので自分では実感しにくいんです(笑)。でも毎日お米はもちろん、何らかの発酵食品は食べていますし、おかげで健康ですね。新潟のお米はおいしいですし。それに、大晦日に神社に行くと甘酒をいただくことがありますが、飲むととても気分が良くなります。寒いところで温かいものをいただくからそうなのかなと思っていましたが、今思えば薬理効果とまではいえませんが、脳機能をうまく良い方向に動かす何かの働きがあるんだろうなと思います。そのひとつにエルゴチオネインが関係しているのかもしれないですね。
先生は食品の専門家ではないとのことですが、どのような食生活が良いなと思われますか?

やはり、食べることそのものが身体を助けてくれるということに尽きますね。麹は菌が米を食べていろんな酵素や栄養素、ビタミンをつくり、身体に良い影響を与えてくれるわけです。だから日常的にそういうものを食べていくのがいいと思います。食品というのはもともと人間が持っている生体機能をサポートしてくれるものでもありますから、日常の食生活をバランスの良い生活習慣にしていくのが一番じゃないでしょうか。
最初の慢性痛のお話で生活習慣から考えることが大事ということでしたが、そのためには食事が大切で、日本の主食であるコメ発酵食品は日本人にも合っているということですね。

そうだと思います。甘酒や米麹などが美容や便通など、健康に良いという報告はこれまでもたくさんあり、今回は私たちの研究結果でストレスに関係するうつ状態や痛みと、それらを制御している脳機能にどんな影響があるかということを示すことができました。そしてせっかく米どころの新潟にいるのだから、まだまだコメ発酵食品で気になるものについて調べていきたいですし、いろいろなことを明らかにして、コメの価値を高めて貢献していけるといいなと思っています。
先生の研究でコメに関連した食品が注目されて、また食事を通じてウェルビーイングな状態になれる人が増えたらいいなと思います。また、先生の研究分野である痛みやストレスに関係する脳メカニズムや管理法の開発の発展につながることもお祈りします。先生、今日はお話をありがとうございました!
ソラミドごはん管理栄養士から、米麹に関するアドバイス
最後に、米麹の栄養効果や、普段の食事に取り入れるアイデアについて、ソラミドごはん管理栄養士・今井からのコメントをお届けします。
今井裕子
老舗ファブリックメーカーに新卒入社後、自社販売体制の構築に注力。サイト改修、印刷物デザイン、動画作成、SNS運用、イベント出展等広く携わったのち、2022年よりデザイナーとしてスカイベイビーズに参加。ソラミドごはんスタッフ。趣味はすてきな日用品探しと、お絵描き。管理栄養士の資格を持つ。

米麹の栄養効果
蒸したお米に麹菌を加えて発酵させることで作られる米麹は、立派な発酵食品です。ブドウ糖やビタミン類も豊富で、疲れたからだにぴったりな食材です◎
また、食物繊維やオリゴ糖が腸内の善玉菌を増やしてくれるため、腸内環境を整える効果が期待できますよ。
気軽に食卓に取り入れるアイデア
1. 米麹で作るやさしい甘酒
炊いたごはんに米麹とお水を入れて、8時間ほど放置するとごはんのデンプンを麹菌が分解してくれて、自然な甘みの甘酒ドリンクが作れます♪
とろっと優しい甘みの米麹で作る甘酒は、温かくしても、夏場は布で濾して冷やして飲んでもおいしいですよ。
2. 塩麹を使っていつものお肉を絶品に!
塩麹は、米麹から作られる調味料です。
お肉にフォークなどで小さな穴をあけ、塩麹を両面にぬって、ラップやジップロックに入れて数時間置きます。
塩麹のコクやうま味が加わり、塩麹に含まれるたんぱく質分解酵素のおかげで固いお肉も柔らかくなります♪
ぜひ米麹を普段の食卓に取り入れて、健康に役立ててみてくださいね。
こちらの記事もおすすめ
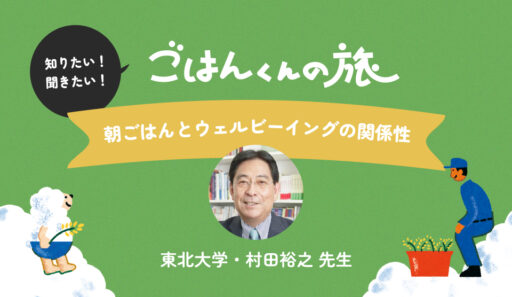



こんにちは。「米麹の摂取は、ストレスが引き起こす不安や痛みを軽減する可能性がある」という研究の発表を見て、お話を伺いにきました。もともと、先生は米麹を研究されていたのですか?