米粉の可能性を探ってみた! -米粉研究家・中村りえさんに聞く、米粉の魅力とは?-

お米を粉末状にした「米粉」は、日本人との関わりが古く、1000年以上も前から和菓子などの材料として用いられていたと言われています。近頃では、健康志向の高まりによって、小麦粉などの穀物から生成されるグルテンを避ける「グルテンフリー」を意識し、取り入れ始める方も増えているようです。
味や食感、使いやすさなどからも、改めて注目を集めている米粉。一度使ってみたいと、気になっている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、米粉料理家として活躍する中村りえさんに、お菓子やパン、料理など幅広いレシピへの活用方法、さらに、米粉が拓くお米の未来についても詳しくお話を伺いました。

お話を聞かせてくれた人
中村りえ さん
管理栄養士、米粉料理家。家族の小麦アレルギーをきっかけに米粉に出会い、そのおいしさと可能性に気付く。自身が運営するブログ「米粉おやつLabo」では、米粉を使ったレシピを多数紹介し、米粉の魅力を発信している。
米粉料理家、中村りえさんが米粉を使うようになったワケとは?

小学校卒業の時には、「将来の夢は管理栄養士」と決めていたという中村さん。中高生になると、口にするものが体にどんな影響を及ぼすのかが気になり、栄養表示なども細かにチェックしていたそうです。
その後、大学を卒業し、晴れて管理栄養士の資格を取得。食品メーカーや健保組合に勤務し、仕事でも生活でも「食物」と「健康」に深く関わりながら過ごしていたと言います。
そんななか、中村さんが米粉と出会うきっかけとなったのが、家族に突然発症した小麦アレルギー。それを機に、小麦粉ではなく「米粉」を使う食生活に切り替えたそうです。
そこで、中村さんはとにかく見よう見まねで小麦粉の代替品として米粉を使ってみることに。しかし、大学時代から熱中していたパン作りで米粉を使ったところ、焼き上がったのは想像とはまったく違うもの。思わず落胆してしまったそうです。そのとき中村さんは、「米粉イコール小麦粉ではない」ということを実感したと言います。
味も食感もまるで違ったんです。小麦粉をそのまま米粉に置き換えてもうまくいくわけではない、ということに気付きましたね。ただ、自分なりにレシピを見直して使い続けると、次第にそのおいしさを感じるようになったんです。
米粉が持つお米本来の味や特徴を活かす使い方、それが大切なんだと感じました。
米粉だからこそおいしい!その特徴・魅力とは?


米粉と小麦粉、どう違うの?
例えば、米粉で「蒸しパン」を作った場合、小麦粉を使用したときよりもパサつきが少なく、逆にもちもちとしたしっとり食感が生まれ、ほんのりと感じる甘さや味の深みもあるのだとか。さらに、クッキーにすればサクサク感がアップし、天ぷらにした場合にはその吸油率の低さのおかげで、カラッと揚がると言います。
使い方次第で風味や食感が楽しめるのが米粉の魅力、と話す中村さんは、その他にも料理に使用する際のメリットを次のように説明します。
米粉は、袋に入ったまま保存してもダマにならない特徴を持っています。小麦粉はお菓子を作る際に、振って粒子を均一にしてから使う必要がありますが、米粉は常にサラサラの状態ですのですぐに使え、時短になるのがメリットです。
それから、普段の料理で感じるのが、米粉は水に溶けるので、ボウルに溶いた後の洗いものがとにかく楽だということ。小麦粉の場合、水を加えるとグルテンが発生して粘りが出るため、洗う際にはしばらく水に浸す必要がありますが、その点、米粉は片付けの手間が省けます。
初心者におすすめする米粉レシピ!


米粉の特徴を知れば知るほど、魅力的なことばかりですね。
では、中村さんがおすすめする「初心者向けレシピ」で、実際にその魅力を体感してみましょう!(※レシピ詳細は、中村さんのブログ「米粉おやつLabo」で公開中)
普段からお菓子作りを楽しんでいる方でしたら、小麦粉を米粉に置き換えてみることからスタートするのが良いでしょう。ただその際は、卵やバターなど生地の膨らみを促す素材を併用することも肝心です。
おすすめはシフォンケーキ。小麦粉だけでは生まれない、ふわもち食感が楽しめます。それから、お菓子作りに慣れていない方には、米粉、卵、牛乳、砂糖などを混ぜて蒸すだけ、わずか15分ほどで出来上がる蒸しパンを試していただきたいですね。
米粉シフォンケーキのレシピ
米粉たまご蒸しパンのレシピ
もちろんパンもおすすめです。小麦粉で作ると発酵が2回、仕上がるまでに2、3時間は必要ですが、米粉パンの場合には発酵は1回のみで15分から20分ほど。作り始めから1時間程度で食べることができます。
米粉食パンのレシピ
それから、普段の料理で試してみたいという方には、手始めにチヂミやお好み焼きなどがおすすめです。小麦粉を米粉に置き換えるだけでボリュームが増し、満足感もアップします。
さらに、シチューにも。ホワイトソースの小麦粉を米粉で代用すれば、ダマにならずに混ぜやすく、とろみも充分。市販のルーを買う必要もありません。
『米粉を一袋買ったけど少しだけ余ってしまい、どう使い切れば良いのかわからない』という声をよく聞きますが、そんなときにはぜひシチューを作ってみてください。
ニラとにんじんの米粉チヂミのレシピ
一度使うと、味や食感、使いやすさなど、色々な良さを感じられる米粉ですが、まずそのおいしさを実感し、段階的に次のレシピに挑戦していくことが大切、と中村さん。
とはいえ、初心者にとっては、どうしても「失敗」への不安が付きまとってしまいます。
そこで、米粉を使う際の「失敗しないコツ」についてもお聞きしました。
米粉を使うときの「失敗しないコツ」とは?
小麦粉を水に溶くと粘りが出る一方、米粉は水に溶けやすく、さらっとしていて粘りが出ないのが特徴だと、先程お伝えしました。つまり、天ぷらや唐揚げの衣に米粉と水だけを使った場合、衣が薄くなったり、揚げ立てはカリッとしていても、時間が経つとおせんべいのように固くなることがあるんです。
そこでおすすめなのが、米粉に片栗粉を加える方法です。こうすることで、カリッとした食感はそのままに、米粉の「油を吸いにくい」というメリットも活かした仕上がりになります。
ご家庭によって、お好みの食感など求めるものが異なると思いますので、まずは基本のレシピを試してみて、そこから自分なりに微調整していくことが失敗しないコツかもしれませんね。
どうしても、最初に失敗してしまうとそこで米粉を使うのをやめてしまう、となりがち。ですが、少しずつ自分オリジナルのレシピへとアレンジしていけば、米粉を使う楽しさも増えていきそうです。
日本人のソウルフード「お米」。その食文化と米粉の未来

加速する「米離れ」に思うこと
さて、ここまで米粉の特徴やその魅力を伺ってきましたが、日々、米粉を使った新たなレシピ開発に情熱を注ぐ中村さんは、昨今の日本人の「米離れ」について、どのように考えているのでしょうか?
お米は日本人にとってのソウルフード。離乳食がおもゆからスタートするように、長く食べ続けているということは、お米は私たち日本人の身体にも合っているという証です。
ですが残念なことに、お米に関わる仕事をするなかで、お米の粒そのものを食べるのが苦手だという方が増えてきている、という印象を持っています。朝食はパン、昼はパスタ、夜は晩酌をするので炭水化物は取らないというように、1日に一度もお米を口にしない方や、なかには炊飯器を持たない方もいます。
もしこのまま米離れが進めば、米農家も減り、お米自体が貴重な存在になるかもしれません。さらに、昨年からの価格高騰が続けば、お米が幻の存在に…。そんなことも危惧しています。
お米をもっと身近な存在にするために、私たちができること
そこで米粉の出番です。お米を食べることが難しいのであれば、代わりに米粉を利用していただきたいですね。
手軽で、使い道にバリエーションがある米粉を取り入れることは、お米の消費率も高めます。農林水産省のデータによれば、国産米粉パンを1人が1ヶ月あたり5枚食べると、食糧自給率が1%アップするそうです(※)。米食を見直すきっかけにもなり、お米がより身近なものと感じられるはずです。
お米の未来を拓くために、多くの方に米粉を手に取っていただきたい。そのためにも、米粉のレシピなど、その魅力を発信し続けていきたいと考えています。
※ 参考:農林水産省「米粉をめぐる状況について」P.10
https://www.maff.go.jp/kyusyu/seiryuu/komeko/attach/pdf/240202-1.pdf
米粉研究家・中村りえさんを取材してみて
米粉は、健康に加え、味や食感、使いやすさという点からも、今後ますます注目が増していきそうです。その魅力と可能性を知ることは、日本に根付くお米文化の継承にもつながると感じます。中村さんの話を聞いて、米粉を身近に感じた人も多いはず。まずは一度、米粉を使ってみることから始めてみませんか?
取材・執筆:福島和加子
こちらの記事もおすすめ
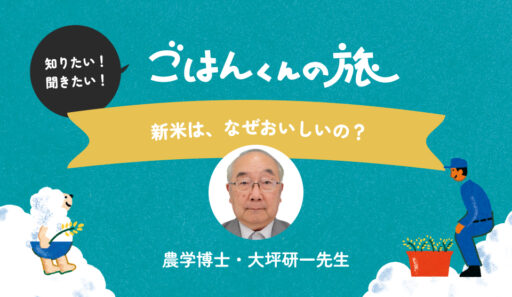



それが2015年頃のことです。当時、米粉を取り扱っていたのは大手のスーパーくらいで、価格も今よりずっと高かったですね。SNSもまだそれほど浸透してなく、米粉のレシピもインターネット上ではなかなか見つかりませんでした。